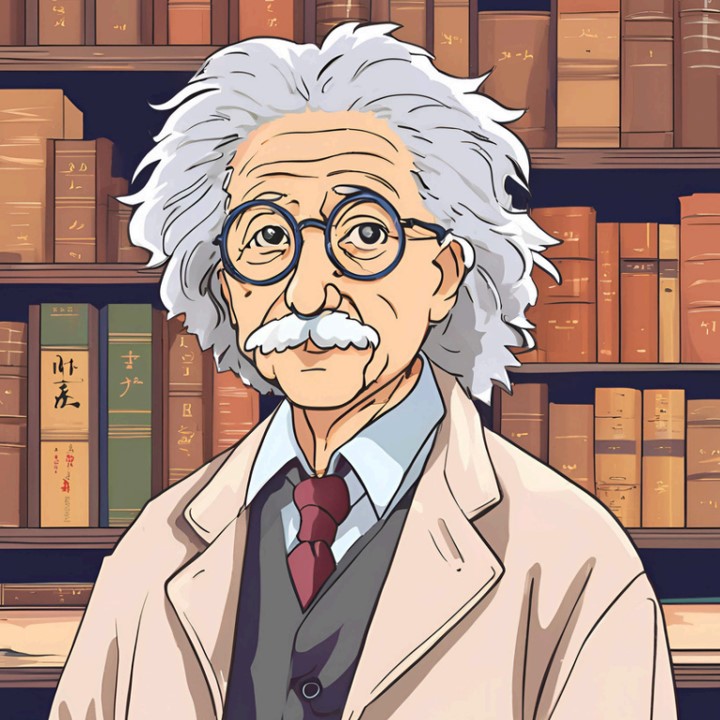
どのような方に読んでほしいか
-
肩の痛みに悩む患者さんを日々診ている理学療法士、医師、柔道整復師、鍼灸師、トレーナーの方
-
姿勢と痛みの関係性について、最新のエビデンスに基づいた情報が欲しい方
-
患者さんへの説明や治療アプローチの根拠を探している方
-
慢性疼痛における姿勢の役割について関心がある方
肩の痛み、特に肩峰下インピンジメント症候群(SAPS)は、多くの患者さんが経験する一般的な問題です。その原因として、しばしば「姿勢の悪さ」、特に胸椎の過剰な後弯(円背)が挙げられることがあります。しかし、本当に胸椎姿勢は肩の痛みに影響を与えているのでしょうか?そして、姿勢を改善することは、肩の痛みや動きにどのような影響を与えるのでしょうか?
この疑問に答えるために行われた、Barrettらによる最新のシステマティックレビューの内容を、医療従事者の皆様に向けて詳しく解説します。
【YouTube】
論文中の「肯定的な意見」と「否定的な意見」
このシステマティックレビューに含まれる個別の研究や従来の仮説には、胸椎姿勢と肩痛・機能・ROMの関係について、以下のような「肯定的な意見」(関連性や影響を示唆)と「否定的な意見」(関連性や影響が低い、あるいは不明瞭)が混在しています。
-
過剰な胸椎後弯は、肩痛の素因と考えられている。
-
少量の胸椎後弯増加は、肩甲骨の挙上および前方傾斜の安静時肢位と関連し、これにより肩峰下腔が減少するという仮説がある。
-
胸椎の湾曲は、筋付着部を介して、または肩甲骨に付着する筋の長さ-張力関係を変化させることで肩甲帯に影響を与える可能性があるという仮説がある。
-
山本ら(2015)の横断研究では、理想的な姿勢で腱板断裂の有病率が最も低く(2.9%)、円背・腰椎前弯姿勢で最も高かった(65.8%)。
-
リスクの高いバイアスを持つ1つの研究では、肩痛のある群が有意に大きな胸椎後弯を示した (p < 0.05)。
-
胸椎後弯を減少させる(より起立した姿勢をとる)ことで、最大肩関節ROMが大きくなるという強いエビデンスがある。これは痛みのある人でもない人でも同様に見られた。
-
高リスクバイアスの研究では、Wall Occiput Test (WOT) 陽性(胸椎後弯増加または可動性制限の指標)がSISの診断と有意に関連していた。
-
高リスクバイアスの研究では、WOT陽性(胸椎後弯増加または可動性制限の指標)と肩関節屈曲ROMが150°未満であることとの間に有意な関連があった。
-
他の研究では、胸椎可動性がSIS患者で対照群より有意に少なかったと報告されている。
-
他の研究では、胸椎の静的後弯に差がないにもかかわらず、SIS患者で胸椎の分節可動性のより大きな制限が観察されたと報告されている。
-
肩痛と胸椎姿勢の関係性については不確実性がある。
-
肩痛のある群とない群の間で、静的な胸椎後弯に有意な差はないという中等度のエビデンスがある。
-
低リスクバイアスまたは中等度バイアスの研究を含め、多くの研究が肩痛の有無で静的胸椎後弯に有意差がないことを報告している。
-
肩甲骨の向きとSAPSの役割に関するエビデンスは不十分であるというレビュー結果がある。
-
静的休息位の胸椎後弯の程度と、肩関節の屈曲または外転のROMとの間には低い関連性しか見られなかった研究がある。
-
崩れた姿勢から起立位への姿勢変更によっても、肩の痛みの強さに有意な変化は認められなかった研究がある。
-
胸椎後弯は、肩痛の発生に対する重要な寄与因子ではない可能性がある。
-
慢性疼痛におけるCNSの感作が重要な場合、静的な胸椎姿勢は痛みの要因としての役割が相対的に低下する可能性がある。
-
理想的な脊椎姿勢が存在し、そこからの逸脱が肩痛を引き起こす、または寄与するという仮説に異議を唱える所見がある。
論文の要約
肩痛は非常に一般的な筋骨格系疾患であり、長期にわたる可動域制限、機能障害、痛みを伴うことが少なくありません。臨床で最も多い肩痛の原因は、肩峰下インピンジメント症候群(SAPS)と報告されており、これは肩峰周囲の非外傷性疼痛で、腕の挙上時に悪化するものです。SAPSは、インピンジメント、滑液包炎、腱板疾患などを包括する用語として広く採用されています。
従来、過剰な胸椎後弯(ハイパーサイフォシス)は肩痛の素因と考えられてきました。過去の研究では、完全な両側肩関節屈曲には約15°、片側肩関節屈曲には約9°の胸椎伸展可動性が必要であること、また大きな胸椎後弯のある高齢者では腕挙上が低下することが示されています。
胸椎後弯が肩に影響を与えるメカニズムとしていくつかの仮説が提唱されています。一つは、少量の胸椎後弯増加が、痛みのない人でも肩甲骨をより挙上・前方傾斜した安静時肢位にさせ、これにより肩峰下腔を減少させる可能性があるというものです。もう一つは、胸椎の湾曲が、筋付着部を介して、また肩甲骨に付着する筋の長さ-張力関係を変化させることで肩甲帯に影響を与える可能性があるというものです。しかし、これらの仮説を支持するエビデンスは乏しいとされています。
最近の研究では、肩のインピンジメントモデル自体が広く疑問視されており、機械的過負荷、変性、遺伝、ライフスタイル要因、さらには中枢神経系(CNS)の関与といった多様なメカニズムが肩痛の発生において重要である可能性が示唆されています。肩甲骨の向きとSAPSの関係についても、エビデンスは不十分であるとするシステマティックレビューの結果もあります。
このような背景から、脊椎姿勢と肩痛の関係についてはかなりの不確実性が残されています。本システマティックレビューの目的は、胸椎後弯と肩痛、機能、および可動域(ROM)の関係に関する現在利用可能なエビデンスレベルを確立することです。具体的なリサーチクエスチョンは以下の2点です。
-
肩痛のある群とない群の間で、胸椎後弯に違いはあるか?
-
胸椎後弯の変化は、肩痛、機能、およびROMにどのような影響を与えるか?
本レビューは、システマティックレビューおよびメタアナリシスの報告に関するPreferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)声明に従って実施され、PROSPEROに登録されました。
研究の特定と選択のため、2人のレビュアーが独立してMedline, CINAHL, AMED, SPORTDiscus, PsycINFO, PsycARTICLES, General Science, Biomedical Reference Collectionの計8つの電子データベースを検索しました。検索には、「shoulder」「spin*」「kypho*」「postur*」などのキーワードの組み合わせが使用されました。
適格基準を満たす研究は、以下の通りです。
-
胸椎姿勢と肩痛、ROM、または機能の関係を検討している。
-
(i)痛みのない対照群がある、または(ii)より胸椎後弯が大きい/少ない2つの異なる姿勢を比較している。
-
英語で出版されている。
-
姿勢変更を目的とした介入(例:姿勢指導)の効果を比較する実験研究も含む。
除外基準には、肩痛以外の痛みが含まれる研究、胸椎姿勢に特化せず脊椎全体の姿勢を検討している研究、英語で利用できない研究などが含まれます。観察研究と実験研究の両方が含まれました。
含まれた研究のバイアスリスクは、Ijaz et al. (2013)によって検証された標準化されたチェックリストを用いて、2人のレビュアーが独立して評価しました。このチェックリストは10の項目で構成され、主要ドメイン(暴露の定義、評価、信頼性、分析バイアス、交絡因子)と副次ドメイン(脱落、評価者盲検化、選択的報告、資金提供、利益相反)に分けられました。暴露(exposure)は胸椎後弯と定義され、低リスクと判断されるには客観的な測定、信頼性の報告、年齢・性別の交絡因子への考慮が必要でした。
含まれた研究のデザイン、参加者、姿勢、アウトカム測定値に関するデータが抽出されました。研究デザイン、参加者、アウトカム測定値にばらつきがあったため、データのプール(メタアナリシス)は行わず、van Tulder et al. (2003) によるエビデンスレベルアプローチを用いてデータを統合しました。エビデンスレベルは、複数の高品質研究で一貫した所見があれば「強い」、低品質研究または1つの高品質研究で一貫していれば「中等度」、1つの低品質研究または利用可能な研究が1つのみであれば「限定的」、複数の研究で所見が不一致であれば「相反する」と定義されました。
検索の結果、合計10件の研究(参加者2794人)が本レビューに含まれました。
【研究デザインとリスク・オブ・バイアス】
含まれた研究のうち6件は、肩痛のある群とない群の間で胸椎後弯を比較する横断研究でした。残りの4件は、姿勢の違いが肩ROMに影響するかを調べる同一参加者反復測定デザインでした。 含まれた研究のバイアスリスク評価では、低リスクが4件、中等度が3件、高リスクが3件でした。多くの研究で、統計的検出力不足やパワー計算の欠如、評価者の盲検化が行われていない、利益相反が報告されていないなどの方法論的な弱点が見られました。
【胸椎後弯の測定方法】
研究によって様々な測定方法が用いられていました。Flexicurve ruler、gravity-dependant manual inclinometerは比較的信頼性が高い方法として使用されていました。他にMetrecom Skeletal Analysis System、Wall Occiput Test (WOT)、超音波トポグラフィも使用されていましたが、一部の信頼性は報告されていませんでした。特にWOTは、静的な湾曲だけでなく胸椎の可動性を反映する可能性が指摘されています。
【胸椎後弯と肩痛の関係】
肩痛のある群とない群の間で、安静時の胸椎後弯を比較した研究は6件ありました。結果として、中等度のエビデンスとして、胸椎後弯の増加と肩痛の間に関連性はないことが示されました。低リスクバイアスの研究を含め、ほとんどの研究で、肩痛の有無による静的胸椎姿勢に有意差は見られませんでした。 ただし、高リスクバイアスを持つ1件の研究(Otoshi et al., 2014)のみが、Wall Occiput Test (WOT) 陽性(胸椎後弯増加または可動性制限の指標)がSISの診断と有意に関連していると報告しました。この研究は方法論的な弱点があり、WOTが静的湾曲だけでなく可動性も測る可能性が指摘されています。
【胸椎後弯の変化と肩機能の関係】
レビューに含まれた研究の中には、姿勢(胸椎後弯の変化)が肩の機能に与える影響を調べた研究は一つもありませんでした。
【胸椎後弯の変化と肩ROMの関係】
研究は少ないながらも、強いエビデンスとして、崩れた姿勢(胸椎後弯が増加した姿勢)は、肩関節の最大ROM(屈曲および外転)の減少と関連していることが示されました。これは、痛みのある人でも、痛みのない人でも同様に見られました。
例えば、痛みのない参加者を対象とした研究では、より起立した姿勢に比べて崩れた姿勢で肩関節の屈曲、外転、外旋ROMが有意に減少しました。痛みのある参加者(SAPSまたはSIS)を対象とした研究でも同様に、起立した姿勢で崩れた姿勢よりも肩屈曲ROMが有意に改善することが示されました。胸椎のテーピングを用いて胸椎を伸展させた研究でも、安静時の姿勢と比較して、SIS患者および痛みのない群の両方で最大肩ROMが有意に増加しました。
ただし、これらの姿勢変更が肩の痛みの強度に与える影響を調べた研究では、姿勢変更による痛みの強さの有意な変化は認められませんでした。
静的な胸椎後弯の程度と肩ROMの関係については、関連が低いとする報告と、WOT陽性(後弯増加/可動性制限)とROM制限に有意な関連があったとする報告があり、結果は一致していません。
本システマティックレビューの最も重要な知見は、中等度のエビデンスとして、静的な胸椎後弯の増加と肩痛の間には関連性がないという点です。この結論は、低リスクバイアスの研究を含む複数の研究の結果に基づいています。ただし、含まれた研究には方法論的な弱点が多く含まれるため、強い結論を出すことはできません。特に、統計的検出力不足や評価者盲検化の欠如といった問題が見られました。これらの限界を考慮すると、従来の「過剰な胸椎後弯は肩痛の主要な原因である」という考え方に対して、疑問を投げかける結果であると言えます。
一方、強いエビデンスとして、胸椎後弯を減少させる(より起立した姿勢をとる)ことで、肩関節の最大ROM(特に屈曲と外転)が即時的に改善することが示されました。これは、肩痛のある患者さんでも、痛みのない人でも同様に見られた一貫した所見です。このROMの改善は、肩甲骨の位置変化(より後傾・外旋位)や、それに伴う肩峰下腔の変化、さらには胸郭周囲筋の活動変化などが影響している可能性が推測されますが、正確なメカニズムはまだ不明瞭です。
しかしながら、これらの姿勢変更によるROM改善は、単一セッション(一度の評価)での結果に基づいています。姿勢変更が、肩の痛みの強度そのものや、長期的な肩の機能や痛みにどのような影響を与えるかについては、本レビューでは明らかになりませんでした。特に、肩機能への影響を調べた研究は皆無でした。
医療従事者としては、これらの結果を踏まえ、患者さんの評価と治療に当たることが重要です。静的な胸椎姿勢の評価は臨床で広く行われていますが、本レビューの結果は、静的な後弯の程度のみをもって肩痛の原因と断定することには慎重であるべきであることを示唆しています。肩痛は多因子性であり、機械的要因だけでなく、変性、ライフスタイル、さらには中枢神経系の感作といった慢性疼痛プロセスが関与している可能性も考慮する必要があります。特に、症状が長期化している患者さんにおいては、痛みの感覚修飾や心理社会的要因など、CNSが痛みに果たす役割が大きい可能性があります。
したがって、臨床現場においては、静的な姿勢の評価に加えて、動的な姿勢(動きの中での胸椎や肩甲骨の動き)、胸椎の可動性(静的後弯だけでなく)、そして個々の患者さんの症状が姿勢変更によって即時的に変化するかどうかを評価することが推奨されます。例えば、Lewisによって提唱されているShoulder Symptom Modification Procedure (SSMP)のように、様々な姿勢や動きの変化が患者さんの痛みに即時的に与える影響を評価するアプローチは、姿勢リハビリテーションの必要性や方向性を検討する上で有用かもしれません。
今後の研究としては、静的な姿勢と痛みの因果関係や長期的な影響を明らかにするための前向きコホート研究、および胸椎の姿勢または可動性への介入が肩痛や機能の改善に有効であるかを検証するための高品質なランダム化比較試験が強く求められます。
この論文の限界点
-
含まれた研究の数が比較的少なく、全体的なエビデンスの蓄積が十分ではありません。
-
多くの含まれた研究において、統計的な検出力不足、評価者盲検化の欠如、利益相反報告の欠如など、方法論的な弱点が見られました。
-
研究デザインの多くが横断研究または単一セッションの介入研究であり、静的な胸椎姿勢と肩痛の間の因果関係や、姿勢介入の長期的な効果を判断するには限界があります。
-
レビューは静的な胸椎姿勢(後弯の程度)に焦点を当てており、胸椎の動的な可動性(動きやすさ)が肩痛や機能に与える影響については対象外でした。他の研究では、可動性の方が重要である可能性も示唆されています。
-
姿勢変更が肩の機能(日常生活動作など)に与える影響を調べた研究は皆無でした。
-
姿勢変更によるROMの改善は即時的な効果として認められましたが、これが長期的な臨床アウトカム(痛みや機能)に繋がるかは不明瞭です。
-
姿勢変更によるROM改善のメカニズムは完全には解明されていません。姿勢を変えることは、胸椎だけでなく頸椎や腰椎のカーブ、さらには様々な筋の活動にも影響を与えるため、どの要素がROM変化に寄与しているか特定が難しい側面があります。
この論文から読者が得られるポイント
-
静的な胸椎後弯の程度だけを見て、「姿勢が悪いから肩が痛い」と単純に判断することには科学的根拠が乏しい可能性があります。
-
肩の痛みがない人でも、姿勢によって肩の可動域は即時的に変化します。より起立した姿勢は、特に肩の屈曲や外転の可動域を増加させる傾向があります。
-
肩の痛みがある人でも、姿勢(胸椎後弯の程度)を変えることで肩の可動域が改善する可能性があります。
-
ただし、姿勢を変えることによって、直ちに肩の痛みが軽減するとは限りません。
-
肩痛の評価においては、静的な胸椎姿勢だけでなく、動的な姿勢、胸椎の可動性、さらには患者さんの痛みが姿勢や動きによって即時的に変化するかどうかを詳細に評価することが重要です。
-
肩痛は姿勢だけでなく、筋力、可動性、インピンジメント以外の機械的要因、心理社会的要因、中枢神経系の感作など、様々な要因が複雑に関与して発生・持続している可能性を考慮する必要があります。
-
姿勢矯正に過度に焦点を当てたアプローチは、現在のエビデンスだけでは肩痛に対して必ずしも有効とは言えないため、患者さんの個別の状態に応じたアプローチを検討する必要があります。
ブログの要約には間違いや個人的な解釈が含まれる可能性があります。 論文の詳細が気になる方、もっと詳しく知りたい方は、是非論文を一読ください。
【本記事で要約した論文情報】
Barrett E, O’Keeffe M, O’Sullivan K, Lewis J, McCreesh K. Is thoracic spine posture associated with shoulder pain, range of motion and function? A systematic review. Manual Therapy. 2016 Oct;26:38-46. DOI: 10.1016/j.math.2016.07.008.【本論文中で引用されている関連論文(一部抜粋)】
Crawford HJ, Jull GA. The influence of thoracic posture and movement on range of arm elevation. Physiother Theory Pract. 1993;9:143–8.
Yamamoto A, Takagishi K, Kobayashi T, Shitara H, Ichinose T, Takasawa E, et al. The impact of faulty posture on rotator cuff tears with and without symptoms. J Shoulder Elb Surg. 2015;24:446–52.
Lewis J.S., Green A, Wright C. Subacromial impingement syndrome: the role of posture and muscle imbalance. J Shoulder Elb Surg. 2005a;14(4):385–92.
Lewis J.S., Wright C, Green A. Subacromial impingement syndrome: the effect of changing posture on shoulder range of movement. J Orthop Sports Phys Ther. 2005b;35(2):72–87.
Bullock MP, Foster NE, Wright CC. Shoulder impingement: the effect of sitting posture on shoulder pain and range of motion. Man Ther. 2005;10:28–37.
Lewis JS. Subacromial impingement syndrome: A musculoskeletal condition or a clinical illusion? Phys Ther Rev. 2011;16(5):388–98.
Otoshi K, Takegami M, Sekiguchi M, Onishi Y, Yamazaki S, Otani K, et al. Association between kyphosis and subacromial impingement syndrome: LOHAS study. J Shoulder Elb Surg. 2014;23:300–7.
Theisen C, van Wagensveld A, Timmesfeld N, Efe T, Heyse TJ, Fuchs-Winkelmann S, et al. Co-occurrence of outlet impingement syndrome of the shoulder and restricted range of motion in the thoracic spineda prospective study with ultrasound-based motion analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:135.
Ijaz S, Verbee J, Seidler A, Lindbohm ML, Ojaj€arvi A, Orsini N, et al. Night-shift work and breast cancere a systematic review and meta-analysis. Scand J Work En-viron Health. 2013;39(5):431–47. (バイアスリスク評価ツールの文献)
van Tulder M, Furlan A, Bombardier C, Bouter L. In: Updated method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group. The Cochrane library. Oxford; 2003. p. 1290–9. (エビデンスレベル評価の文献)
Ratcliffe E, Pickering S, McLean S, Lewis J. Is there a relationship between sub-acromial impingement syndrome and scapular orientation? A systematic re-view. Br J Sports Med. 2014;48:1251–6.
Butler DS, Moseley GL. Explain pain. Adelaide: Noigroup Publications; 2003. (CNSの役割に関する文献)




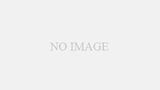
コメント